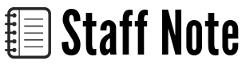2004.10.19
映画『コラボレーター』の描いたこと(後編)
Posted by :早尾貴紀
(前編の続き)
しかし、この映画の監督が本当に映し出したかったことは、もっと別のことであったように思います。
映画では、「こうした彼らのドン底生活の中にも、涙と笑いがあり、彼らも自分たちと同じ人間なのだ」と感じさせることを意図した場面がいくつか登場します。例えばムーサが、同居しているロシア人女性らを両わきにはべらせてカメラに向かって語りかける場面。社会の底辺、除け者同士が、寄り添いながら生きているとか、そこにも人生の一部をなす男女関係があるのだ、ということを映し出します。またムーサが、泡風呂の中から顔だけを出して楽しげにしながら来客に居留守を使う場面は、観客の笑いを誘います。あるいは、30歳の誕生日を迎えたマジッドが、その日は昼間から不平タラタラで、人生投げやりというところを見せますが、夜にムーサやロシア人の同居女性らからケーキと花輪を贈られ、誕生日を半ベソをかきながら複雑な気分で祝います。
いちばん監督の意図がはっきり表れていたのは、半ば「観客」的な人物が登場する次のシーンかもしれません。ムーサがある内務省か警察の待合室のベンチで、連れのロシア人女性を待っているところ、隣に何かの用事で来たイスラエル兵が座ります。尋問というわけではなくたんなる世間話で兵士が聞いてきます。
「あなたの仕事は?」
「コラボレーターさ(笑)」。
冗談と思ったのかその質問を軽く聞き流して、
「子どもはいるの?」
「12人ほど」
「うわぉ!(笑)」
「ガザではみんな子だくさんなんだよ」
「え? 本当にガザ出身なの??」
「だから言ったろ、コラボレーターだったって(笑)」
「噂では聞いたことがあったけれど、初めてホンモノを見たわ。コラボレーターって、みんなどうしようもない犯罪者だって聞いていたけれど・・・」
「ガザで犯罪なんてしたことはないよ。コラボレート(イスラエルへの密告・協力)した以外には(笑)」
こうしてこの兵士は、不意に遭遇した元コラボレーターが、「普通の人間」であることを発見するのです。おそらくそれは、この映画を観た多くのイスラエル人が同じ事実を発見するプロセスと重ねられているように思います。
映画祭であったため、上映後に若いイスラエル人監督(もちろんユダヤ人)の挨拶がありました。そこで彼女が強調していたことは、自分がこの映画で描きたかったのはヒューマニズムだ、ということでした。彼らはそれでも生きている、それでも同じ人間だ、私たちと同じ街の中でしかし知られることなくひっそりと生きているのだ、と。確かにそれはそうでしょう。会場は大きな拍手に包まれました。
しかし、僕は、そして僕といっしょに観に来ていたフラットメイトのパレスチナ人(イスラエル国籍)は、大きな違和感を抱いて外に出ました。
「どう思った?」と彼は聞いてきました。
「あの映画は元コラボレーターの生活を描いたけれども、コラボレーションそのものは何一つ描いていない。ムーサに置いていかれた家族はいまどうしている? 子どもや妻は、親戚や近所から冷たい視線にさらされているんじゃないか。マジッドが殺した3人はどうだ? どんな人で、その家族は何を考えているのか、監督は気にもしていないようだし、またそれはユダヤ人の監督には中に踏み入って取材をすることも無理だろう。だから、あの映画が描いているのは、コラボレーターについての事実の半分だけだし、残りの半分は隠蔽しているとも言えると思う。」
それに対して彼曰く、
「映画そのものについては、まったくそのとおりだと思うけれど、僕がもっと気になったのは、観客たちの反応だ。観客の90パーセントはユダヤ・イスラエル人だろう。残りは欧米の外国人。自分以外にただの一人もアラブ・パレスチナ人を見つけることはできなかった。つまりあの映画は、そういう観客に向けて作られた映画だということだ。良心的なイスラエル人が、自分たちこそは社会に批判的で人権意識が高いと思い込んでいて、きっとほとんどが労働党とかメレツを支持している穏健和平派で、シャロンなんかには反対なんだ。だけれども、この映画がもたらした効果は何だ? たんにこういう映画に感動をする自分自身に酔い痴れているだけじゃないのか。監督と観客のあいだには最初からそういうお約束ができているかのようで、気持ちが悪い。ヒューマニズムなんてクソ喰らえだ!」
彼が観客はユダヤ人ばかりだと言ったことは、もちろん一人一人を確認することなどできませんから、完全にそうかどうかは分かりません。ただ、中東系のユダヤ人(ミズラヒーム)は外見上はアラブ人と区別することは難しいという事実を鑑みると、そこにいた観客のほとんどは、イスラエル社会の上流階級をなすヨーロッパ系のユダヤ人(アシュケナジーム)だということになる、ということは確かでしょう(彼はアラブっぽい顔つきの人を一人も見なかったと言ったのですから)。そして、彼らが労働党などの穏健和平派の支持層をなしているというのは、そのとおりです。まさにこの映画は、そういう客層の消費物として供されたわけです。
それに関連して、もう一つ印象的な場面を思い出しました。ムーサやマジッドや同居人らがテレビを見ていたら、アルジャジーラのニュースでコラボレーターの公開処刑シーンが流されていた(それをイスラエルの放送局が流していたのかも)、という場面。これは明らかに、この映画自体の「ヒューマニズム」と対比して、「野蛮」と映ったことでしょう。「イスラエル国家が、ひいてはイスラエル国民である自分たちが、パレスチナ人の元コラボレーターを人間として見ているというのに、パレスチナ人はひどいことに、仲間を裏切り者として処刑をしている、残虐である」、というように。もしそういう意図が監督にあり、また実際にそういう効果を観客にもたらしたとすれば、これはひどい倒錯だということになると思います。
この点を見ても、この映画の消費構造は、いやらしい錯誤に満ちていると感じてしまいました。そして、この同じ錯誤は、イスラエルのいわゆるシオニスト左派知識人(アモス・オズやダヴィッド・グロスマンに代表される)や彼らの信奉者らの言説消費構造(その消費者は日本にもいる!)にも通じている、ということにも注意が必要であるように思います。