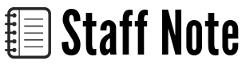2005.02.18
パレスチナに関係があるのかないのか、二冊の本
Posted by :早尾貴紀
昨年暮れ、ちょうど同時に刊行されたある二冊の本について書いておこうと思います。パレスチナに関係があるのかないのか微妙な二冊の本、厳密に言うと、パレスチナに関係がありそうでなさそうな一冊の本と、パレスチナに関係がなさそうでありそうな一冊の本、の二冊について。前者が、井沢元彦『ユダヤ・キリスト・イスラム集中講座--宗教紛争・テロはなぜ終わらないのか』(徳間書店)。後者が、ノーマン・フィンケルシュタイン『ホロコースト産業 --同胞の苦しみを「売り物」にするユダヤ人エリートたち』(立木勝訳、三交社)です。
まず前者の井沢『ユダヤ・キリスト・イスラム集中講座』について。これはデカイ新聞広告を出して鳴り物入りで売り出されたものらしいのですが、その新聞広告にも帯にもこんな売り文句が書かれています。「日本人には、一神教原理で動く人々のことが決定的にわからない!」「超大国アメリカの世界戦略、イスラエル・パレスチナ問題、テロとの戦い、、、すべてがみるみるわかるようになる!!」と。この時点で断言します。この本は有害無益、買うべからず。
ここのパレスチナ情報センターに来られる方々には、改めて「パレスチナ問題は宗教紛争じゃないんですよ」なんてことは言うまでもないことだと思います。それは事実認識として間違いだというだけでなく、イスラエル側にとって都合がいいプロパガンダです。というのも、「宗教だ」と言えば、「神の名のもとに、一つの土地を奪いあっているのね」とか、「信仰を賭けて、どちらも譲れない戦いをしているのね」とか、そういう話になる。そうすれば、「じゃあ戦争になるのは仕方がないし、そして戦争なら強いほうが勝ち、勝ったほうが正しい」ということになり、結局そういう認識は、圧倒的な軍事力を持ったイスラエルの占領行為を「いちがいには批判できない」というように、消極的であれ是認することにつながってしまいます。
井沢氏の『ユダヤ・キリスト・イスラム集中講座』という本が、こういった偏見を無意識に共有してしまっているのか、あるいは世間に流通しているこういったステロタイプにおもねっているのか、あるいは意識的に偏見を煽っているのかは、よく分かりませんし、いずれの場合でも、この本が有害無益なことに違いはありません。そしてもう一言加えておきたいのは、この本には、パレスチナに関わる歴史や政治や経済といった基本的な知識が欠如しているだけではなく、著者が主眼としている「宗教」それ自体についても通俗的な誤解と偏見を上塗りすること以上のことはできないだろうということです。「宗教がわかれば紛争がわかる」なんていうのは、たんなるウソなのですから。
正直、こういった本の存在に言及をすることさえ、むしろ本の知名度をあげてしまうのではないかという危惧も感じたのですが、この本が「売れている」という話も聞いたことがあるので、やはりダメなものはダメだと、そしてこれ以上売り上げに貢献をしてはならないと、あえて言うべきだと思いました。あ、ちなみに僕は本屋でサラッと立ち読みをした程度です。
さて、もう一冊の本、フィンケルシュタイン『ホロコースト産業』についてです。この本が主題としているのは、アメリカのエリート層のユダヤ人らが、いかに「ホロコーストの記憶」を政治経済的に利用し利益を得ているか、ということですから、直接的にはパレスチナ問題には関係ありません。でも、関係がなさそうに見えて、実は深い深い関係があるように思えます。
まず最初にありうる誤解を避けるために言っておきたいのですが、著者は決してガス室否定論者などではありません。ホロコーストの記憶や歴史が政治経済的な駆け引きの道具として利用されることだけを問題にしているのです。また、彼がユダヤ人虐殺そのものについてどれだけ真っすぐに向き合っているかは、彼の両親がまさにワルシャワ・ゲットーと強制収容所を体験した生き残りであるということと、それから彼が著書の中でラウル・ヒルバーグというホロコースト研究の世界的第一人者の仕事を最大級に評価をし、また逆にこの大家ヒルバーグがフィンケルシュタインの告発の意図を正確に理解し支持していた、という事実に端的に表れていると思います。ともかくも、批判されたアメリカのユダヤ人利権集団は著者を「ガス室否定論者」とレッテル貼りをし、反対に本当の否定論者からはそのレッテルによって誤解を受けて妙な歓迎をされてしまっているという、悲しむべき事態があるようですが、著者本人の主張はそういうこととはまったく無縁なところにある、ということは確認しておきたいと思います。
さて本題ですが、フィンケルシュタインの重大な主張の一つはこういうものです。いまやホロコーストと言えば、他のいかなる民族差別とも比較しえない唯一無二の絶対的な悪である、という認識は一般的になっている。そして、ユダヤ人を批判する者は、その批判がいかなるコンテクストを持つ場合でも、ホロコーストを楯に取られ「反ユダヤ主義者」のレッテルを貼られ、一切の批判がはねつけられてしまう。ところが実際には、ホロコーストが何らかの特権を持って語られるなどということは戦後しばらくはなかったのであり、ホロコーストが政治・経済的に利用価値のあるものとして脚光を浴びたのは、イスラエルにおいてさえ1961年のアイヒマン裁判を待たなくてはならず、アメリカにおいては1967年の第三次中東戦争でのイスラエルの大勝を待たなくてはならなかった。と、こういうことを著者は主張しています。
第三次中東戦争というのは、イスラエルが圧倒的な軍事力でシナイ半島やヨルダン川西岸やゴラン高原を占領し大勝をした戦争です。これ以降イスラエルは、中東におけるアメリカの前哨基地としての重要性を高め、またアメリカのユダヤ人にとっての精神的な拠り所としても認められるようになりました。アメリカからイスラエルへの軍事費や武器などの支援の肥大化も、このあたりから始まっています。イスラエル国内でも広大な占領地の獲得は、文字通りの「神懸かり的な」大勝として宗教的な意味附与がなされ、イスラエルの存在は「ホロコーストの贖い」として認められるようになりました。ここにおいて、ホロコーストの語りが政治経済的な重要性を持つものとして表舞台に表れます。ホロコーストは、アメリカ社会の中でエリート層にのし上がったユダヤ人と中東世界の軍事大国にのし上がったイスラエル国家とが、ともにそれでも自らを歴史の「被害者」としてアピールしあらゆる批判を回避するための、格好の口実となったのです。
なお、著者フィンケルシュタインの主眼は、むしろアメリカのユダヤ人団体が利益集団・圧力集団として凶暴化していき、本当の直接的なホロコーストの犠牲者や遺族をダシにして暴利を貪っていく、そのプロセスの分析のほうに置かれますので、パレスチナ問題はそれほど焦点とはなっていません。しかしここでは、あえてパレスチナのコンテクストに引き付けて、もう一言加えておきたいと思います。
イスラエルの占領政策の批判も、思想運動としてのシオニズム批判も、ほとんど門前払いをされるかのように、「反ユダヤ主義」とか「ホロコーストの否定」などというレッテルを貼られて封じられてしまいます。具体的かつ限定的な批判さえも、「ホロコーストの神聖性」を楯に取られて拒絶されてしまうのです。例えばそれは僕自身の経験としてもあります。1996年に仙台でパレスチナ人映画監督ミシェル・クレイフィの『石の賛美歌』の上映会を企画し、ちょうどその直前に仙台で開催されていた「心に刻むアウシュヴィッツ展」でも映画のチラシを置いてもらえないかと主催者にお願いをしたところ、露骨に拒否をされてしまいました。当時のアウシュヴィッツ展のパンフには、こういうことが書いてあったと思います。「アウシュヴィッツの体験は普遍的です。アウシュヴィッツに耳を傾けることは、あらゆる差別に耳を傾けることなのです。」と。であれば、パレスチナの声にも耳を傾けてください、と言ったのですが、彼らにとっては、「パレスチナ」という名は、アウシュヴィッツの神聖性を汚すようなものとして感じられたのかもしれません。
そういうことで、この『ホロコースト産業』という本は、いつから・どのようにして、ホロコーストの絶対性とか神聖性といった概念がイスラエルやアメリカのシオニストらによって作られ利用されるようになったのか、ということを知るために、一定の有益な視角を提供してくれると思います。そして、それがいかにパレスチナ問題の公正な認識を阻害しているか、ということも。パレスチナ問題を知ろうという人にはやや遠回りで細かすぎる本かもしれません。しかし、『ホロコースト産業』は、最初に紹介をした井沢『ユダヤ・キリスト・イスラム集中講座』などよりも、はるかに誠実で有意義なことは確かだと思います。
最後に余談ですが、『ホロコースト産業』の中に出てくる一文、「痛烈な皮肉と言うべきだろうが、ユダヤの知識人で1967年6月以前にイスラエルとの連帯を公言していたのは、ハンナ・アーレントとノーム・チョムスキーの二人だけだった。」(p.31)というのを読んだときには、思わず笑ってしまいました。アーレントとシオニズムとの関係については一定知られていると思いますが、とくに「9・11」以降に反戦平和・アメリカ批判のヒーローとして祭り上げられているチョムスキーが、実は「正統な」シオニストだっていうことは知られていない(忘れられている)と思います。
付記
『ホロコースト産業』については、以下でも紹介があります。
P-navi info 何でも反ユダヤ主義──世界ユダヤ人会議のキャンペーン