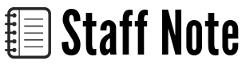2006.03.10
「中道」政党「カディマ」って何だ?
Posted by :早尾貴紀
現在病に倒れ事実上政界を引退したアリエル・シャロン首相が、まだ健在だった昨年末、リクード党を離脱し、新党「カディマ(カディーマ)」を結成したが、シャロンが倒れた後もなお、今月末に迫ったイスラエル総選挙で、定数120のうちの三分の一の約40議席を獲得し、第一党となる見通しとなっている。この数字は過半数には達しないものの、小党/多党の乱立状況にあるイスラエルの国会(クネセト)にあっては、第二党・第三党となる労働党とリクード(いずれもかつては二大勢力をなしていた)がそれぞれ20議席には達さないと見られており、その意味でカディマは、「新党」としては異例の大躍進と、劇的な「政界再編」を果たすと言われるゆえんである。
そもそもシャロンがリクードを離脱せざるをえなかったのは、「ガザ撤退」に象徴される、パレスチナからの「一方的分離」政策が、与党リクード内部で強い反発にあい、再三政策修正などの妥協を強いられるなど、内部から足を引っ張られることが重なったことが背景にある。そうした中、(主要入植地を残すなど欺瞞だらけながらも)「占領地からの撤退」という要素を含む「一方的分離」政策は、従来の労働党の政策と重なるものであり、労働党からも支持を得ていた。実際、シャロン首相がガザ撤退案をぶち上げ、ネタニヤフなどのリクード内強硬右派からの突き上げをくらって危機に瀕していた04年頃には、労働党の支持基盤である「ピース・ナウ」などの和平団体がシャロン支持の大規模なデモを繰り広げていた。その点、左派・和平推進派がタカ派の(元)軍人シャロン将軍を支援するという奇妙な光景が見られたが、これはその後の「中道」政党「カディマ」の誕生を予見させる出来事であったと言えよう。
タカ派で知られるシャロン首相は、しかしながら、老獪で現実主義的な政治家でもあった。党内の勢力争いから何度も足を引っ張ろうとするネタニヤフらよりも、自分のほうが国民的な支持を受けているという確信と、そしてシモン・ペレスら数人の労働党議員らの合流や支援の約束によって、シャロン首相はリクードに見切りをつけて、新党を立ち上げる決心をした。そもそもシャロンは、リクードという右派連合を1973年に誕生させた立役者でもあり、その意味では、自らが作った党を自ら壊し、しかも現職首相が自ら与党を飛び出すという、大胆不敵な行動をとったことになる。
たしかに、こうした経緯・背景からすれば、メディアが「カディマ」を「中道」政党であると形容するのも頷けるところではある。リクードを「右」、労働党を「左」とすれば、その「あいだ」であるからだ。しかし、カディマの大半がリクード出身者であるという現状を見れば、まだ「リクード1」と「リクード2」と言ってもいいような状況であり、他方で、カディマの「一方的分離」がそもそも労働党の政策の焼き直しであることを見れば、「労働党1」と「労働党2」とも言える。カディマの実態は、左右の「中間」なのではなく、「リクード=労働党」とも言うべき、むしろその二党の共通基盤の上に成り立つ政党ととらえるべきであるように思われる。つまり、リクードと労働党は、私たちが新聞報道などで受ける印象の、右対左という対立図式にあるよりも、むしろ共通しているもののほうが大きいのだ。その共通基盤というのは、「一方的分離」の意図が、和平ではなく、あくまで「シオニズム=純ユダヤ性の堅持」であることから明らかだ。労働党・リクード・カディマは、「シオニスト政党1・2・3」にすぎない。
このことは、イスラエルにおける、あるいはイスラエル建国前のパレスチナにおける、シオニズムの諸党派/政党の歴史を改めて振り返ると、よく見えてくる。シオニズムの主要な流れは、その後労働党とリクードにつながっていく、そのそれぞれの前身諸党派に整理できる。
シオニズムにはさまざまな流れがあると言われる。政治シオニズムだとか、宗教シオニズムだとか、実践シオニズムだとか、文化シオニズムだとか、修正主義シオニズムだとか、、、しかし、ここではそんな区分は重要ではない。混乱を招くだけなので、二つのカテゴリーだけを用いる。その際、「右」と「左」というのも、誤解を招く表現であるように思う。というのも、一般に「左」というのは和平派というニュアンスを帯びるが、シオニスト左派の場合は、シオニズム運動そのものが侵略的な入植運動であり、左派だろうが右派だろうがその一翼を担ったことに変わりはなく、その意味では「左=和平派」などではありえないからだ。
「現実路線」と「急進路線」というのがわかりやすいかもしれない。労働党の流れを遡るとダヴィッド・ベングリオンが、リクードの流れを遡るとウラディミール・ジャボティンスキーが、それぞれ大きな役割を果たした祖として浮かび上がる。いずれもが、すでにアラブ=パレスチナ人という先住民のいるパレスチナの地にユダヤ人だけの国家を建設するという、文字どおり「途方もない企て」に挑むにあたって、何が最善・最短であるかを考え実行してきた。一人でも多くのアラブ人をパレスチナの地から放逐し、最大限の領土を勝ち取る、というシオニズムの「原則」を両者は共有していた。何をどうしたって、先住民の排除の上にしか成り立たないユダヤ人の集団入植は、暴力的手段を伴わずにはいられなかった。その点に両者の差異はない。
では、ベングリオン派とジャボティンスキー派の違いは何か。ベングリオンらは、「土地所有と国家建設を国際社会から承認してもらうことなしに建国はありえないのだから、欧米諸国との利害関係には配慮をしつつその後ろ盾を得ることが、建国への近道である」、と考えた。いわば「現実路線」だ。その際、暴力的手段を排除したわけではない。おおっぴらにはしないで、国際社会の目を気にしつつ、可能な範囲で実力行使をしたのである。
他方、ジャボティンスキーらは、そうした姿勢を生温いとして批判し、より過激な姿勢を取った。問題はそのための手段であり、パレスチナ人を武力で脅かし、委任統治期にはイギリス当局に対しても武力行使をためらわず、破壊活動の継続でもって心理的な圧力をかけ続けることが、ユダヤ人国家を手に入れる近道であると考えた。彼らの軍隊(イルグンなどが知られる)は国際社会から「テロリスト」と呼ばれることをためらわなかった。目的達成の手段としてテロリズムに開き直っていたのだ。いわば「急進路線」だ。
さて、両者に差異はあるか。本質的には「ない」とも言える。入植村を「前哨基地」として海岸から内陸へ内陸へと侵攻し、占領を既成事実化することで土地収奪をするという戦略も同じだ(これがいまのグリーンラインを形成する。グリーンラインは「停戦ライン」ではない)。武力行使も程度問題にすぎない。国際社会の目をどのように気にするか、の違いでしかない。現実路線のベングリオン派は、国際協調をタテマエとしつつ、その目を盗んで侵攻を続けた。急進路線のジャボティンスキー派は、武力行使をむしろ国際社会に見せつけることで、影響を与えることを目指した。
その両者が対立関係にあったわけではない以上、そのどちらが正しかったか、有効だったかということではない。おそらく、相互補完的な効果があり、暗黙のうちに役割分担をしてきたというのが実情だ。そのどちらもが、同じく真正シオニストであり、侵略行為に開き直っていたのだから。それを「左対右」という対立図式でとらえることは、誤読となるように思う。
この「現実路線」の流れがいまの労働党に、「急進路線」の流れがいまのリクードに到る。
アリエル・シャロン首相こそは、その路線の違いを統一する人物であった。ただ、そもそも両者に本質的な違いがないのだから、統一は難しいことではない。そもそも差異のない主張を、一つの手段にまとめあげただけのことである。「分離壁」も「一方的撤退」も実は労働党政権下ですでに探られ提案されていたものであった。リクード党首だったシャロンは第二次インティファーダに便乗して政権奪回をすると、そうした政策を修正しつつ取り入れていった。「手段」はここでほぼ類似する。新党カディマはそこに位置する。
したがって、新党カディマは決して、「左」と「右」の「中間」に位置する「中道政党」などではない。「リクード2」にして「労働党2」でもある、もうひとつの「真正シオニスト政党」にすぎない。
シャロン氏は、不謹慎な言い方をすれば、絶妙なタイミングで政界を去り、「平和の人」という称号を手に入れ、後にはリクード党も労働党も置き去りにするような強い「中道政党」を残した。あまりに出来すぎの神話が世界中のマスコミを覆いつつあるのが気がかりだ。もう一度、シオニズムの歴史を振り返りつつ、カディマの本質を見失わないようにしたい。
付記: 『世界』4月号 に小田切拓氏の「アリエル・シャロン--かくして、彼は絶大になった。」という記事が掲載されている。このスタッフ・ノートでは、カディマの来歴に重点を置いたが、小田切氏の記事では、いまのパレスチナの現状と今後の分析がなされている。重要な論点が提示されているので、ご一読を。