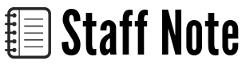2007.05.23
シオニズムはリベラルになりうるのか――ヤエル・タミール『リベラルなナショナリズムとは』をめぐる勘違い
Posted by :早尾貴紀
◇ヤエル・タミール『リベラルなナショナリズムとは』
(押村高、高橋愛子、森分大輔、森達也訳)、夏目書房、2006年12月
* * *
私事になりますが、昨年アイザイア・バーリン論を書きました。バーリンとは、政治学分野では知られたリベラリズムの思想家です。が、同時に労働党とピースナウに肩入れをしていた強固なシオニストでもありました。彼のなかで、リベラリズムとシオニズムはどう両立していたのか、それを論じたのです。
そして、ここで取りあげる『リベラルなナショナリズムとは』のヤエル・タミールは、そのバーリンの教え子です。この著書の元は、バーリンのところで書かれた彼女の博士論文でした。バーリン論を書いたときに、まだ日本語訳の出ていなかったその著書もザッと読んで言及もしました。一読、ある意味でたいへんにつまらない本だと思うと同時に、シオニズム左派の欺瞞を典型的に示すものとして(つまりは悪い見本として)わかりやすい例だな、と思いました。よもやこんなつまらない本を全訳する人が出てくるとは思ってもいませんでした。後述するように、シオニズム批判の素材とする以外には理論的貢献など皆無のこんな本を翻訳紹介するなど、意味がないと思っていたのです。出版されたときは、奇特な人もいるものだな、としか感じませんでした。
が、話はそう簡単ではなさそうです。著名な社会学者さんらが、次々と好意的な書評を書きはじめたからです。曰く、
「ナショナリズムを非合理なものとして頭から否定するのではなく、その論理を粘り強く抽出し、リベラリズムとの接合可能性を探る。(中略)著者が採る「リベラルなナショナリズム」という立場は、英米リベラリズムを自家薬籠中のものとしつつも、どこまでもネーションというものに拘わらざるをえない著者のポジションに由来しているように思える。もちろん全体としてクールな論理に貫かれているのだが、クールな筆致が逆に著者のホットな問題意識を浮かびあがらせているようにもみえる。」(北田暁大:朝日新聞2/18)
「民族が運命の問題ではなく、文化を通じて想像された共同体の問題だとするなら、多様性を許容することも可能ではないのか。著者は(中略)、イスラエルの政治家としては、ナショナルな価値を否定することは到底できないが、一方で、排他的な立場も政治学者としては許容できない。パレスチナ人との融和を唱える著者は、政治的現実を踏まえて「リベラル・ナショナリズム」という理念を提唱したのである。」(桜井哲夫:東京新聞3/4)
もちろん訳者らも評者らも、タミールが、和平団体ピースナウの創設期メンバーであり、労働党の政治家であり、オルメルト内閣の閣僚であることを知っているわけです。そう、タミールは、イスラエルの「良心的左派」を代表する研究者兼活動家兼政治家なのです。ええ、占領地でのパレスチナ人への弾圧にも心を痛めていることでしょう。典型的なシオニスト左派です。
で、訳者・評者らは「シオニスト左派」であるということが、いったいどういうことなのかを、何かしら知っているのでしょうか? とてもそうは思えないほどのナイーブさを感じます。タミールの経歴でことさらに言われる、「ピースナウ創設期メンバー」。それを聞くと一般的には、「ああ、イスラエルのなかにも、和平を求める人がいるんだ。こういう良心的な人の存在が大事なんだ」という意見がしばしば聞かれます。
しかし、ピースナウとは、占領政策を批判はしますが、イスラエル国家のユダヤ性については微塵も疑うことのない確固たるシオニスト団体です。西岸地区やガザ地区における入植地の拡大や、イスラエル軍兵士やユダヤ人入植者によるパレスチナ住民への暴行には関心を払い、調査を行ない、心を痛めはしますが、その程度の「良心的団体」にすぎません。国際的に非難を浴びている東エルサレムの占領・併合を批判したことさえなく、「Land for Peace」(占領を終結させてパレスチナとの和平を進めよ)を掛け声にするわりには、東エルサレムも含めた入植地の無条件の全面撤去を主張することもありません。せいぜいが、「ユダヤ人国家としてイスラエルを承認するなら、いくつかの入植地撤去を進めましょう」という、しみったれた条件付きの和平案です。つまりは、イスラエル国家の「ユダヤ的性格」は不可侵のものとすることと、東エルサレムやグリーンライン沿いの主要入植地については「存置」すること、これがピースナウの方針です。
ヤエル・タミールさんがどれくらいリベラルでいらっしゃるかご理解いただけたでしょうか。
話をタミールの師匠、アイザイア・バーリンに戻します。バーリンは、ラトビア生まれでイギリスに移住をしたユダヤ人で、イスラエルへは移民をしませんでしたが、生涯を通して強固なシオニストでした。ハイム・ワイツマン初代大統領、ダヴィッド・ベングリオン初代首相と親交が厚く、何度となく、イスラエルに移民をし政治家になるようにと要請がありましたが、本人は、イギリスを中心に世界を飛び回る学者兼外交官というポジションに身を置いていました。
そのバーリンは、リベラリズムに関しては、押し付けがましい積極的リベラリズムから区別された、「・・からの自由」とも定式化される消極的リベラリズムを主張し、また、ナショナリズムに関しても、攻撃的・排他的ナショナリズムを批判し、それと区別された、民族アイデンティティの根拠となる文化的ナショナリズムを擁護しました。「消極的リベラリズム」と「文化的ナショナリズム」、これがバーリンの思想を特徴づけるものです。
ここで明らかなように、タミールの「リベラル・ナショナリズム」というのは、つまりこのバーリンの思想をもう少し肉付けして理論化したものです。
バーリン自身は、年齢的なこともあってか、終生イスラエルへの移民を拒みつづけたものの、思想的には、シオニズムを強固に保持していました。そのシオニズムは、バーリン思想の根幹である上記の「消極的リベラリズム」と「文化的ナショナリズム」に基づき、同時にまたワイツマンやベングリオンらとの人間的繋がりから、のちの労働党につながる「シオニズム左派」と呼ばれるものでした。
老バーリンは、その後もベギン、シャミル、シャロンといった代々のリクード党首を害悪だと非難し、労働党政権下でオスロ和平合意を結んだイツハク・ラビン当時首相の支持を公言しました。オスロ合意は1993年、ラビン暗殺は95年、そしてバーリンの死去は97年のことです。
ところで、この「左派」という政治的ラベルが、「和平派/穏健派」という誤解のそもそもの根源なのですが、結論的に言えば、実のところ、競合していた「シオニズム右派」との本質的な違いはありません。たんにそれは急進度の差しかなく、いずれにせよ、パレスチナ人をパレスチナからできるだけ多く放逐し、できるだけ多くのユダヤ人を移民・入植させ、ユダヤ人国家を建国し、その領域を最大化させる、そして建国されたユダヤ人国家イスラエルの内部に残るパレスチナ人コミュニティの増加・発展はできるだけ押さえつけ、イスラエルのユダヤ性をできるだけ純粋なものとしていく。この点においては、左派であろうと右派であろうとまったく同じなのです。違いはと言えば、どれだけ国際社会の目を気にするか、の一点。左派は欧米諸国の協力を得るべく、批判を気にしながら民族浄化を進めてきました。右派は、あからさまな原理主義を掲げて、いかなる手段を用いることをも正当化してきました。左派グループはのちに労働党につながり、右派グループはのちにリクード党につながるわけです。(そして建国前であれ建国後であれ、現実にパレスチナ人の追放や占領・破壊をより徹底的に遂行したのは左派である、という点も忘れるべきではありません。)
それは同時に、バーリンの「リベラルな文化的ナショナリズム」が、実のところ、攻撃的・排他的ナショナリズムと本質的差異がないことの証左でもあるのです。タミール同様、バーリンも、ピースナウへのコミットメントを誇示していましたが、しかしやはりそのことと矛盾することなく、徹底してイスラエルのユダヤ的性格を不可侵のものとして擁護し、そして東エルサレムのイスラエルへの併合も支持しつづけました。これは、イスラエル国内のパレスチナ人に対等な人権を認めないということであり、リベラリストであるどころか、純然たるレイシストであること、そして文字どおりに攻撃的で排他的なナショナリストであることをこそ露呈してしまっていると言えます。
ヤエル・タミールはこのバーリンに師事し、そしてカディーマ中心の連立内閣の閣僚を務めています。皮肉にも、「リベラル・ナショナリズム」の本質が、そこに見事に体現してしまっている、と言うべきでしょう。
師バーリンが十全に理論化しなかったリベラリズムとナショナリズムの問題を、師に代わって一書にまとめあげたのが、この『リベラルなナショナリズムとは』でした。ともにシオニスト左派で、労働党とピースナウにコミットしていた二人の立場は、しかしより端的には、「リベラルなシオニスト」というべきもので、このように書くと、その奇怪さは明瞭です。「リベラル・シオニズム」をより説明的にすれば、「リベラルな装いでパレスチナ人差別・弾圧を正当化すること」です。現実のイスラエル国家においてシオニズムとは、どこまでも徹底的に「対等な権利主体」としてのパレスチナ人存在の否定です。イスラエル国内にいるパレスチナ人だろうと、東エルサレムにいるパレスチナ人であろうと、占領地にいるパレスチナ人だろうと、あるいは国外難民となったパレスチナ人であろうと、ユダヤ人と同等の権利をもってパレスチナ/イスラエルに住む権利が認められることはありません。この点は、繰り返しますが、労働党だろうとピースナウだろうと、そうなのです。「イスラエルのユダヤ性を最大限に認めるかぎりにおいて、それを妨げないかぎりにおいて、部分的かつ従属的にのみ、パレスチナ人の権利を考慮してやってもいい」というのがバーリン、タミールなどシオニスト左派の立場であり、右派はもっとわかりやすく単純に「パレスチナ人はいなくなってほしい」と言います。言っていることは同じなのですが。
ともあれ、「リベラル・シオニズム」とぶち上げてしまっては、対外的に正当性を説明するのが難しいところもあるので、より普遍性を装って、理論的に正当化するための道具が「リベラル・ナショナリズム」だったのです。
さて、訳者や評者らは、これくらいのリアリズムをお持ちなのでしょうか? どうも机上の空論を楽しんでいるようにしか思えません。もちろん学者さんが理論を可能性の領域でいじくるのは勝手ですけども、あまり安易に現実世界に足がついているようなフリをしてものを言わないでほしいとは思います。「クールな論理/ホットな問題意識」? 勝手に言ってやがれ。シオニズムをリベラリズムに無理やり接合しようというだけで理論的にもホットすぎて沸点を超えて吹きこぼれています。他方でタミールの問題意識は、シオニズムの擁護という点で、冷徹・冷酷です。クールよりも寒く、コールド、フリーズってカンジです。言葉遊びもたいがいにしやがれ!
最後に冒頭で触れた拙論について。昨年は10月から11月にかけてパレスチナ/イスラエルに行っていたのですが、11月4日がバーリンが信頼を寄せその死を悔やんだイツハク・ラビン当時首相が暗殺された日(1995年)、そしてその一日後の11月5日がバーリン自身の命日(97年他界)でしたので、イスラエルでその日を過ごしていました。とくにラビンの命日は毎年盛大な式典が行なわれます。昨年はレバノン戦争の直後であり、政治的混乱が激しかったために、ラビン時代への懐古的な思い入れがいっそう強かったように思います。
そうしたなかで、たまたまバーリン著作集を持ち歩き、タミールの英書も持ち歩き、夜に時間のあるときには読んで論文の準備を進めていました。11月半ばに日本に戻り、もう少し資料調べをして、11月末日の締切直前の数日で書いたのが、「アイザイア・バーリンにおけるシオニズムとイスラエル――「リベラル・ナショナリズム」の理念と現実」(『UTCP研究論集 第10号』東京大学)です。論文ですが、11月上旬の二つの命日の空気を色濃く反映しています。
この拙論は、早尾貴紀『ユダヤとイスラエルのあいだ――民族/国民のアポリア』(青土社、2008年)の第7章に再録されました。ぜひお読みください。