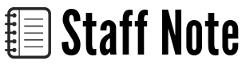2007.05.30
「多文化主義」から考えるシオニズムと天皇制
Posted by :早尾貴紀
最近、「多文化主義」ということについて考えることがあります。それを政策的に明確にしているところとしてはカナダとオーストラリアが有名ではありますが、結局のところ、「純粋な単一文化」の国家などありえないわけですから、普遍的な問題だと言っていいと思います。事実、大筋においてはなお「単一民族」説がなお根強いここ日本においてさえ、行政サイドから「多文化」の言葉が発せられるようになってきています。少子化・労働力不足に起因するにせよ、人口移動の流動性の高まりに起因するにせよ、ともかく定住外国籍者の数や出身地域の多様性が増す一方であるという現実があり、その現実を日本の保守的な政治家や行政側も追認せざるをえなくなった、というわけです。
しかし、日本というところには、「市民権」という考え方がありません。カナダやオーストラリアにおいて、多文化主義が政策的な争点になるときにまず問われるのは、「市民権」です。マジョリティの民族・文化への同化や国民への帰化という原則を立てずに、すなわち多様性を肯定しながら平等な市民権の附与を行なうということが求められているのです。そのカナダやオーストラリアにおいても、しかしながら、市民権をめぐる議論はレイシズムを免れてはおらず、多様性の全面的な肯定ということにはなっていません。市民権は、保守主義者には、なお移民の排除と包摂(つまり従順に取り込まれなければ排除する、という圧力)の道具として使われうるのです。近年、こうした問題は思想的な問いとして鋭い議論に晒されており、たとえば、ガッサン・ハージ『ホワイト・ネイション』(保苅実・塩原良和訳、平凡社、2003年)などは大切な批判的視点を示しています。
さて、そのはるか手前にある日本、市民権という発想そのものが欠如している日本で、「多文化主義」を行政が口にするとき、いったい何が想定されているのでしょうか。
おそらく、同じ「多文化」という表現を使っていても、念頭に置かれている内実はバラバラで、それはおおまかに以下の三つに分類されうると思います。
(1)個々の民族や文化の純粋性というものが確たる不動のものとして前提され、それらが混じり合うことなく、一つの国家ないし共同体のなかである程度存在している。
(2)個々の民族や文化の純粋性は、異なる民族や文化との接触によって変容しうる。
(3)そもそも「純粋な一つの民族/純粋な一つの文化」といった概念そのものが、政治権力によってつくられ操作されうるものである、という批判的意識。
あきらかに日本の行政が発する「多文化」は、上の(1)に入るでしょう。しかも、その複数の文化はたんに並んでいるだけではなく、圧倒的マジョリティの「日本人/日本文化」が確固として支配層として存在しており、その他マイノリティはそれを侵さない付属物としてだけ存在を許される、その「許容」の度合いを少しばかり高めて、ちょっとは「寛容」になりましょう、と。いまさまざまな外国人労働者の政治的な導入が議論されていますが、それは、あくまで日本社会の純粋性を侵害しない程度までであるとされるわけです。すなわち、もっとあからさまな言い方をすれば、なお外国人は日本に居てほしくない人、という排他的本心が役人や政治家、そしてマジョリティ日本人にはあるでしょう。
それに対して、積極的に多文化社会論などを提言している人びとが想定するのは(2)の文化変容。文化が複数存在する、というのではなく、国境を越えた文化同士の接触が新しい文化を生み出し、それがまた文化的な豊かさになっていく、という肯定的な考え方です。
ただし、よくよく歴史的にかつ思想的に掘り下げて考えてみると、(3)の次元に行き着くことは不可避だと思うのですが、いまはその議論はおいておきます。
前々回のノート、「シオニズムはリベラルになりうるのか」の問題を考え直します。『リベラルなナショナリズムとは』という形で、シオニズムの寛容精神を訴えた著者ヤエル・タミールと、その翻訳者らや書評者たちは、どこまで自覚があるのかは分かりませんが、ともあれ、イスラエル国家におけるユダヤ人至上主義、つまりシオニズムを不可侵の絶対的原理として認めつつ、少し寛容になりましょう、と言っています(「そんな単純なことは言っていない」という反論もありえましょうが、断固として却下です)。上の分類で言えば(1)です。イスラエルのユダヤ人でシオニストのタミールは、典型的なシオニストであり、かつ労働党の政治家であり、オルメルト内閣の閣僚だということで、まあいいでしょう(よくないですが)。
しかし、それを賞讃する訳者さんらや好意的な書評を寄せた社会学者さんらは、いま自分が属し生活をしている日本社会をどう考えているのでしょうか。タミールへの評価に照らして言えば、(1)にしかなりようがありません。それはつまりは、保守的な日本の行政と同じ土台に乗っているということでもあるのです。横柄なことに、「マイノリティたちにも少しは寛容の心を見せてやろうか」という姿勢をリベラルだと自任して憚ることのない役人たちと変わるところがない。
だとしたら、彼らに問いたいのは、「天皇制はリベラルになりうるのか」ということです。あるいは、『リベラルな天皇制とは』という本でも編んでほしい。その結論・回答は、こうなるしかないでしょう。
(注:これは引用ではありません。先の二つの書評から、単語を入れ替えつつ作成した文章です。ちなみに、日本における「帰化」とは、「戸籍」の取得のことであって、国籍=市民権の取得ではありません。戸籍が登録される先は、居住地でも出生地でもなければ「国家」でさえなく、国家の象徴である「天皇」になっています。その証左に、登録される対象である皇族自身だけは戸籍に入ることがありません。日本において「帰化」で求められるのは、厳密に言えば「国民」になることではなく、「臣民」になることです。)「天皇制を非合理なものとして頭から否定するのではなく、その論理を粘り強く抽出し、リベラリズムとの接合可能性を探る。天皇制が多様性を許容することも可能ではないのか。日本人としては、天皇制の価値を否定することは到底できないが、一方で、排他的な立場も社会学者としては許容できない。移民や在日外国人との融和を唱える我々は、政治的現実を踏まえて「リベラル天皇制」という理念を提唱する。これがクールな論理に貫かれたホットな問題意識というものだ。」
「多文化主義天皇制」や「リベラル天皇制」など、私にはとうてい受け入れられそうにない議論です。しかし、これこそがいま、日本社会のリベラルな方々に浸透している考え方なのだと思います。もしタミールの『リベラルなナショナリズムとは』にお金と時間を費やすことに意味があるとするならば、鏡として反面教師として、日本の「ネオリベ」とか「新保守主義」と言われる潮流について思考を凝らすことなのかもしれません。