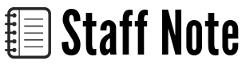2008.08.25
パレスチナの二人の詩人――ダルウィーシュとアル=カーシム
Posted by :早尾貴紀
マフムード・ダルウィーシュが亡くなった 。日本でもある程度は知られているパレスチナ人の詩人であった(とはいえ一冊しか翻訳詩集が流通していないが)。世界的な知名度で言ったら、間違いなくもっとも著名なパレスチナ詩人だ。
1941年にガリラヤ地方のビルワ村に生まれ、48年のイスラエル建国時に村を破壊され、一時的にレバノンに避難したのち、翌年に、イスラエル領となった同じガリラヤ地方の別の村に「帰還」。1960年に第一詩集を刊行してから60年代には何冊かの詩集を出版し、一躍、パレスチナを代表する詩人として高く評価された。
だが同時に、イスラエルからは、パレスチナ人の民族意識を、ひいては抵抗運動を高揚させるとして危険視され、投獄や自宅軟禁といった政治弾圧を受け続けた。結果として、71年にダルウィーシュはイスラエルを、すなわちパレスチナの地を離れることとなった。「イスラエル国民」であるにもかかわらず、正規のパスポートが発給されず、暫定的な渡航許可証のみでの出国となり、事実上、帰国を許されない亡命であった。
その後、ベイルート、カイロ、チュニス、モスクワ、パリなどを転々としながら、旺盛な詩作活動を継続していった。とりわけ、ベイルートとチュニスでは、PLOの要職に就いて組織の仕事もしていた。だが、1993年のオスロ合意を受けて、その内容に失望。PLOの職を辞した。
とはいえ、オスロ合意がもたらしたPLOによるパレスチナ暫定自治政府の発足は、ダルウィーシュとパレスチナの地との関係を複雑にした。95年に暫定自治がヨルダン川西岸地区の主要都市にまで拡大されると、パレスチナ自治政府は拠点をラマッラーに移したが、ダルウィーシュもまた同じくラマッラーに「帰還」を果たす。生地ガリラヤへの帰還ではなかったが、広い意味でのパレスチナへの「帰還」だ。
小さな街ラマッラーで、再度拠点を同じくすることとなったPLOとダルウィーシュとの関係はぎこちないものとなったと言われる。オスロ合意批判を、ひいてはPLO批判をしたダルウィーシュに対して、PLOは文化活動の財政援助をしないなどの圧力をかけていた。それによってダルウィーシュは、公然としたPLO批判を控えざるをえなかったとされる。自治政府とともにラマッラーに拠点を移すということは、そういう政治的な手打ちの関係に身を置くということになる、ということは不可避のことであるように思われる。ダルウィーシュはそれを承知で、しかし、パレスチナへの象徴的な「帰還」を優先させたのかどうか。
ともあれ、こうしたダルウィーシュの生涯は、ある意味で、パレスチナ人の苦難を全身で体験するものとなったと言える。すなわち、イスラエルの「二級市民」としての被差別生活、国外での「難民」としての生活(レバノンだけでなくヨーロッパのパレスチナ人コミュニティでも)、イスラエル軍のベイルート侵攻とそこからの追放、チュニスの亡命政権、そしてラマッラーでも2002年にイスラエル軍による攻撃を経験した。
こうしたなかでの詩作活動は、いっそうダルウィーシュの詩人としての世界的な名声と、パレスチナ人としての代表性とを高めることとなった。
1960年代におけるイスラエル軍政下のガリラヤで、そこでアラブ・パレスチナ人として生きる、生活を営むということ、それ自体のもつ抵抗を初期のダルウィーシュは謳った。それはより直接的なメッセージ性をともなった。「書き留めてくれ/私はアラブ人」のリフレインで知られる詩「身分証明書」、故郷パレスチナを恋人に見立てて愛を謳った詩「パレスチナの恋人」など、いまでも著名な詩だ。
だが、亡命以後、70年代からダルウィーシュはこういった直接的なメッセージを織り込んだ詩を書かなくなった。どんどんと実験的に新しいスタイルを試み、間接的で、(印象としては)私的で、謎めいていて、、、さまざまな技巧を駆使するようになった。訪問・滞在したアラブ諸国で、人びとから60年代の代表的な詩の朗読を求められても、頑なにそれを拒絶したと言われている。自覚的に60年代の自らの表現とは距離を置いていたのだ。
表現の洗練あるいは斬新さが詩として高く評価される一方で、82年のベイルートでの体験、02年のラマッラーでの体験などなど、そのときどきのパレスチナ人の代表的な苦難を背景としていることによって、その都度の新しい詩の発表が大きな注目を浴びた。
* * *
おそらく、その対極に、動かざる/変わらざる詩人として、やや影を潜めてしまったのが、若い頃からダルウィーシュの同志であった サミーハ・アル=カーシム ではないかと思う。アル=カーシムは、ガリラヤにとどまり続けている。60年代は、ダルウィーシュとともに、ガリラヤ地方や都市ハイファなどで、詩作やジャーナリズムの活動をしていた。投獄や自宅軟禁などの苦労もともにした。それゆえにアル=カーシムは、ダルウィーシュの亡命についても深い理解を示している。当時は、ダルウィーシュがイスラエルを、つまりパレスチナの地を離れたことに対して非難の声は少なくなかったという。逃亡である、と。しかし、「詩人が詩を詠むことが犯罪であるとされるのであれば、もはや呼吸をすることさえここではできないではないか。彼は悩みぬいた。私も悩んでいた。結果的に、私は残ることにしたが、彼は離れることにした。しかし、誰がそれを責めることができようか」。
アル=カーシムは、60年代から、ダルウィーシュとともに並び称される抵抗詩人として著名であった。しかし、ダルウィーシュが海外で高い評価を得て、世界的な名声を得ていったのに比べれば、その知名度は低いし、また詩そのものの評価についてもそうだ。 Electronic Intifada にダルウィーシュの追悼を発表した アスアド・アブ=ハリール もまた、ダルウィーシュの詩の絶えざる進化を讃えるために、その比較として、アル=カーシムの詩は「詩的表現において停滞しており発展がない」と評している。
たしかにその指摘は当たっているだろう。そしてその差異は、一面においては純粋にダルウィーシュの才能に起因もしているだろうが、しかし、ダルウィーシュの「移動の経験」がもたらした外部との接触という要因も関わっているように思われる。逆に言うと、アル=カーシムの「詩的表現の停滞」も、そして相対的に影が薄いことも、同様にアル=カーシムがガリラヤに留まりつづけたことと関係しているのではないだろうか。
パレスチナの抵抗運動は、一方でPLO指導部がベイルートからチュニスに移動した後に、他方で1987年に第一次インティファーダが勃発したことによって、運動・闘争の舞台を、レバノンから被占領地であるヨルダン川西岸地区とガザ地区に移した。湾岸戦争やオスロ合意を経て、被占領地にパレスチナ自治政府が発足した。それと反比例するように、イスラエル領内となった地域に残ったパレスチナ人たちは注目されることがなくなり、「本来的なパレスチナ人ではない」というふうに見られるようになっていった。「彼らはイスラエルのなかで安穏として民族意識を失い、闘争に参加していない」、と。
ダルウィーシュは、先述のように、闘争の舞台に合せて、ベイルートからチュニスへ、そして西岸ラマッラーへと拠点を移した。そして結果としては、いったん距離を置いたはずのPLO自治政府との関係を曖昧にさせていった。
アル=カーシムは、旧友で盟友であるダルウィーシュのそのスタンスに対して懸念を示したことがあった。「ラマッラーに住むということは、自治政府と良好なあるいは妥協的な関係を構築するということにしかならない。そして自治政府が自己保身に没頭し、結果としてイスラエルの占領の一道具にしかならないということはわかっていたはずなのに」、と。しかし、アル=カーシムは、そうした懸念を公言することまではしなかった。「マフムードを批判できるのは、私と彼との信頼関係があるからこそであり、同志としての長い時間の積み重ねがあるからだ。そしてこうした懸念も、友人らのなかでしか言うことはできない。さもないと、私とマフムードとの間にありもしない不和をでっちあげようという輩に利用されかねない。スキャンダルを提供したいわけではないのだ」、と。
アル=カーシムは、ダルウィーシュの少し年上で、もうすぐ70歳になろうとしている。イスラエルの反シオニストの活動家からも、もはや一時代前の詩人とみなされ、政治的な立場ももはやさほどラディカルではないと評されている。
しかし、「動かない」ことで「抵抗」を示してきたアル=カーシムが、他方では、誰よりも堅固な批判精神をイスラエルの内部で半世紀以上も保ち続けていることも事実だ。「パレスチナ人」でいること自体が困難を極めるイスラエル国家において、そのアイデンティティを保持しながら闘う心を愚直に変わらず謳い続ける姿が訴えるものは、いまでも十分に大きい。