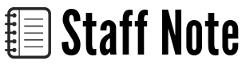2019.05.25
帰還大行進―ガザの市民社会を支え、その変革を主導する女性たち
Posted by :役重善洋
パレスチナ被占領地ガザ地区では2018年3月30日より、「帰還大行進」と呼ばれる大衆的デモ行進が、同地区を取り囲む隔離フェンス周辺で連日行われている。モスクでの集団礼拝が行われる金曜日には、開始当初で数万人規模、現在でも数千人規模の人びとが集まる。これまでに200人以上の参加者がイスラエル軍によって殺害され、2万人以上が負傷させられている。その多くは実弾の直撃によるものである。この平和的デモの参加者への一方的殺戮が日本で報道されることは極めて限られている。報道されたとしても、その内容は相も変わらず、「パレスチナ人のデモ隊とイスラエル軍との衝突」という客観性を欠いた枠組に捉われたものが大半である。帰還大行進が世界に訴えかけているメッセージは、まさにこの民族紛争・宗教紛争という枠組の否定であり、彼らの闘いは植民地解放闘争なのだというものであるにも関わらず、である。
■植民地主義・人種主義を乗り越えるための連帯を求める明確なメッセージこのデモの名称に掲げられている「帰還」とは、1948年5月のイスラエル建国に際して破壊され、イスラエル領とされた故郷の村へのパレスチナ難民の帰還を意味する。ガザ住民の75%は、1948年に現イスラエル領から追放されてきた難民およびその子孫が占めている。彼等が帰還権を要求することは世界中に散在する550万人のパレスチナ難民との連帯をも意味する。この帰還権は、国際法上認められたパレスチナ人の正当な権利であるにも関わらず、「ユダヤ人国家」というシオニズム・イデオロギーの大前提と矛盾するために、イスラエルはこれまで一貫して拒否してきた。同国は、トランプ政権で親イスラエルのスタッフを多く要職に配置することに成功すると、国連パレスチナ難民救済機関へのバッシング・キャンペーンを行うなど、パレスチナ難民という国際法上のステイタスそのものを縮小ないし無効にしようとする努力を加速させてきた。そうした狡猾な政治的圧力を根底から跳ね返そうとする強い意志が、このデモの名称には込められている。
また、帰還大行進は、2007年にハマースによるガザ統治が始まって以来続く同地区への封鎖政策の解除を求めている。イスラエルによるガザ周囲の壁/フェンスの建設は1990年代に始まっているが、2007年以降は、人道支援物資も含め、飢餓状態を引き起こさないための最小限度の物資の搬入しか認めない方針が取られている。加えて、ガザ住民が仕事や留学、治療等のために出域することは極めて困難であり、また、ジャーナリストやNGO関係者、研究者などの入域にも様々な規制がある。こうした人・モノの移動制限は、多数のイスラエル入植地や隔離壁に浸食されている西岸地区では露骨な人種隔離システムという形態を取っている。人々の経済生活に破壊的な影響を与えているという点ではガザも西岸も同じである。これらの政策はいずれも国際人道法・国際人権法が禁じる違法行為にあたる。2002年に西岸地区で建設が始まった隔離壁に対しては、その影響を受ける村・地域ごとに超党派の民衆闘争委員会が組織され、抗議デモなどの非暴力直接行動が継続的に行われてきた。こうした活動は、パレスチナ自治政府と一体化したPLO幹部の官僚主義や各政治党派のセクト主義などを乗り越えようとする志向性をもつものであったが、イスラエルによる手の込んだ分断工作や、活動の長期化による倦怠、パレスチナ自治政府による妨害、外国人活動家の入国拒否等々により、この10年ほどは停滞を余儀なくされてきた。帰還大行進は、西岸地区における隔離壁・入植地反対運動を再活性化させる触媒となる可能性をもっている。
この運動が始まった3月30日という日付にも重要な意味がある。1976年のこの日、イスラエル領内北部のガリラヤ地方における大規模土地収用に反対するデモが行われ、6名の参加者が殺害された。以来、この日は「土地の日」と呼ばれ、イスラエル領内のパレスチナ人だけでなく、被占領地や離散の地にいるパレスチナ人にとって共通の民族的連帯を表明する日とされてきた。帰還大行進はガザ地区の超党派の若手活動家が主体となって始めた運動ではあるが、最初から、厳しい政治的・地理的分断状況にあるパレスチナ人の全民族レベルの連帯・連携を目指すものであった。
さらに、当初この連続デモの最終日とされていた5月15日は、イスラエル建国に伴う故郷喪失(ナクバ)を記憶する日とされており、その前日はエルサレムへの米国大使館移転が決められていた日でもあった。この大使館移転は、イスラエル側からすれば、イスラム教徒に占領された「聖地エルサレム」を解放するという欧米諸国の十字軍的植民地主義/イスラモフォビアとの連携を意味するものであったが、パレスチナ側からすれば、世界中のイスラム教徒との連帯を促進するものであった。
■ナッジャールさんにとって参加は女性抑圧に対する闘い以上、帰還大行進が強く志向するガザ地区の外のパレスチナ社会や国際社会との連帯という側面に注目してきたが、以下では、視点を変えて、ガザ地区内部における社会的連帯という側面からこの運動のもつ可能性について論じてみたい。日本を含めた西側主要メディアではほとんど論じられていないが、運動開始当初から、このデモでは女性の参加率が高いことがアルジャジーラ等、いくつかのアラブ側メディアなどで報じられてきた。性別役割分業が明確なパレスチナ社会では一般的にデモへの女性の参加率は非常に低い。しかし、帰還大行進は、いわゆるデモをするだけでなく、5つに分けられた地域ごとに、炊事班や医療班などが組織され、伝統舞踏やコンサートなどの文化イベントやスポーツ・イベントも開催されている。そして、そこでは女性達が中心的な役割を担っている。
帰還大行進の中で負傷者の手当に献身していた21歳の看護師、ラザーン・ナッジャールさんが昨年6月1日にイスラエル軍によって射殺されたことは日本でも一部メディアで報じられたが、彼女が生前にニューヨークタイムズの記者に答えたインタビューの中に印象的なくだりがある。「私たちの目的は、人々の命を救い、負傷者を救護すること。そして、世界に対して武器がなくても私たちには何でもできるのだというメッセージを伝えることです」。このメッセージには、イスラエルによる植民地支配を打ち砕こうとする民族的主張とともに、このデモがハマースによって扇動されているとするイスラモフォビックかつ人種主義的な主張を覆そうとする洗練された政治的センスを見ることができる。
しかし、さらに彼女の発言を聞き続けると、「何でもできるのだ」という彼女の言葉には二重の意味が込められていたことに気づく。「(ガザの)人びとは父に、娘が給料ももらわずにどうしてここで活動をしているのかと尋ねますが、父は娘を誇りに思うと答えてくれています。・・・私たちの社会では女性はしばしば一方的に(デモに参加すべきでないといった)規範を押し付けられます。しかし社会の側が私たちを受け入れるべきなのです。彼らは私たちを受け入れようとしませんが、いずれそうせざるを得なくなるでしょう。なぜなら私たちはどんな男たちよりも力をもっているからです。それは、私がデモの第一日目にいち早く(看護ボランティアとして)行動を起こすことで示した力です」。
ナッジャールさんにとって、帰還大行進に参加するということは、イスラエルの占領に抗うとともに、ガザの社会における女性抑圧と闘うという意味をもっていた。一般的にガザ地区は西岸地区に比べて保守的な社会だと言われている。しかしその保守性は、現代社会におけるあらゆる「伝統」と同様、政治的に形成・強化された側面をもつ。
帰還大行進に参加する一定の年代以上の人びとは、1987年12月に始まる第一次インティファーダのときの社会的雰囲気を思い起こしている。それは、1993年のオスロ合意によってパレスチナ自治政府が設立される以前の大衆闘争のことで、学校閉鎖に対抗する「地下学校」の組織など、地域に根差した非暴力抵抗の精神が広く共有されていた。そこでもやはり女性のイニシアチブが重要な意味を持っていた。パレスチナ文化センター総連盟代表ファーディー・アブー・シャンマーラと米国人ジャーナリストのジェン・マーロウは、帰還大行進に参加する女性たちへのインタビューから構成した 興味深い記事 を書いている。その中で取り上げられている女性リーダーの一人、サミーラ・アブデルアリームは、自治政府の発足によって、インティファーダの際に力を発揮した地域社会のリーダーシップ、とりわけ女性たちが意思決定過程から排除されていったことを指摘している。2000年9月に始まる第二次インティファーダでは、党派毎の軍事部門による武装闘争が中心となり、とりわけガザ地区ではその傾向が強かった。男性中心の組織動員型運動の中で女性のリーダーシップは著しく弱められた。そうして政治的欲求を押さえつけられてきたガザの市民社会が、政治的行き詰まり状況にあったハマース政権の承認・協力を勝ち取り、実現させたのが帰還大行進である。その動きの中心に、ガザの女性達の存在があることは看過されてはならない。
上記記事が秀逸なもう一つの点は、インタビューした女性たちに、未来のパレスチナ国家においてユダヤ人と共生することはできるか、という質問をしていることである。彼女たちは揃って問題ないと答えている。ちなみに帰還大行進の提唱者の一人である、ガザの詩人アハマド・アブー・アルティーマは明確な一国家論者である。地獄のような状況の中で彼女/彼らが目指す、すべての人間にとってインクルーシブなパレスチナ社会という理想は、英国による占領以来100年にわたる植民地支配をパレスチナに押し付けてきた国際社会に向けた預言的メッセージともいえよう。その声をいかに自分自身の問題として受け止めるかが、日本に暮らす私たち一人ひとりにも問われている。
※『市民の意見』173号(2019年4月1日発行)より転載。
付記:帰還大行進を、ガザの人びとの絶望の表現として捉える 論調 がある。いつ終わるとも知れない封鎖、出口の見えない貧困、国際社会の沈黙、そうした状況に人間が絶望するのは当然のことだ。しかし、より驚くべきこと、注目すべきことは、それにもかかわらずガザの人びとがいまだに希望と創意工夫とをもって連帯の行動を求めるメッセージを国際社会に発信し続けていることではないだろうか。その声を受け止めず、「絶望」の側面ばかりを強調してしまうとすれば、受け手の側の姿勢にこそ「絶望」の原因があるのではないか、と思わざるを得ない。
【参考記事】 帰還大行進を継続するガザの人々を孤立させないために BDS運動を日本でも拡げよう!(長周新聞、2018年12月27日)